불교의 존재론입니다.
우주, 세계 그리고 사람은 무엇으로 구성되어서 존재하며, 활동하는가에 대한 불교적 존재론입니다.
불교를 믿거나 알고 싶은 분은 꼭 참고하십시오!
우리는 물리학에서 우주의 모든 요소가 소립자의 결합으로 되어있고,
화학에서 물질의 구성원소를 멘델레예프의 주기율로 나타내고 있습니다.
이와같이 불교에서도 사람이 무엇으로 구성되어서 존재하고 활동하는가를 밝혀줍니다.
철학으로 말하면 바로 존재론(存在論, Ontologie)입니다.
주로 상좌부불교(=소승불교, 부파불교, 원시불교)에서 다루는 불교의 학설입니다
즉 설일체유부와 아비달마코샤에서 다루고 있습니다.
그러므로 이 학설은 가장 오래된 불교의 이론이며
대승불교의 '중론 中論', '공론 空論'과 다르며,
또한 후기 대승불교인 유식학(唯識學)과도 다릅니다.
한번쯤 이 이론을 알아두시면
불교를 보다 깊이 이해하는데 도움이 됩니다.
진심 이 학설은 유물론과 유심론이
동시에 존재하며
종교와 과학 그리고 철학이 함께 합해져 있습니다.
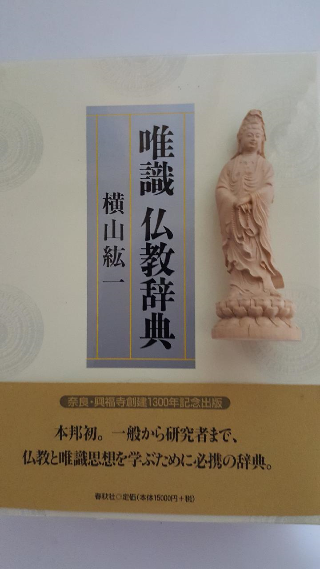
***이하는 삼과(三科 : 불교의 존재론)에 대한 일본의 '위키페디아'의 번역입니다***
이 삼과에 대해서는 한중일의 3가지 글만 위키에 존재하고,
일본의 위키가 가장 정확하고 긴 설명이 있습니다!
삼과(三科)는 불교에 있어서 '세계를 존재하게 하는 일체의 법을 분류한 3가지 범주' : 5온, 12처 그리고 18계이다.
줄여서 온(蘊), 처(處) 그리고 계(界), 또는 음(陰), 계(界) 그리고 입(入)이다. 또한 육근(六根), 육경(六境), 육식(六識)이라는 3범주로 나타낼 때도 있다.
三科(さんか)とは部派仏教における、世界を在らしめる『一切法』を分類した三範疇、五蘊(五陰)・十二処・十八界をいう。蘊・処・界、または陰・界・入と略すこともある[2]。また、六根・六境・六識の三範疇をいうこともある。
目次
五蘊(五陰)・十二処・十八界[編集]
오온(오음)-십이처-십팔계
全ての法は、下記の五蘊の一つの蘊、十二処の一つの処、十八界の一つの界とにおさまる[3]。
모든 법(法, 법=dharma=모든 물질과 마음)은, 아래에 나오는
오온중에서 하나의 온, 십이처중에서 하나의 처 그리고 십팔계중에서 하나의 계에 들어있다.
일반적으로 법은 각각의 자성(自性)을 가진 것이기 때문에,
ある法がそれと別個な自性をもつ他の法の中におさまるということは決して無い[3]。
어떤 법은 그것과 다른 자성을 가진 다른 법속에 들어가 있는 일은 결코 없다.
諸法を五蘊、十二処、十八界と説くのは、
모든 법을 오온, 십이처, 십팔계라고 주장하는 것은,
중생(유정)의 어리석음, 또는 자질,
あるいは希求するところに3通りがあるから、
또는 간절히 원하는 바가 3가지가 있기 때문에,
それらの各々に応ずるためとされる[3]。
그것들 각각에 대응하는 것으로 여겨진다.
また、原始仏典においては、
또한, 원시불교의 경전에 있어서,
我々の全経験領域をさしてこれらを
우리들의 모든 경험영역을 나타내고, 이것들을
一切(梵: sabbam、我々の全経験領域)と呼ぶものの、
일체(범어로 sabbam, 우리들의 모든 경험영역)라고 부르면서,
「我がある」とは明言されず、
'나는 존재한다'라고 말하지 않고,
그러나 그 어떤 것도 무상하고, 고통이고, 비아이고,
그러한 것들을 떠나서 또한 떠나고자 하면 해탈하여 깨닫는다고 한다.
五蘊[編集]
오온
五蘊(ごうん、梵: pañca-skandha) - 五陰(ごおん、旧訳)とも。
五蘊(오온 , 산스크리트어=범어, panca-skandha) - 五陰(오음, 옛날의 번역)등
人間の肉体と精神を五つの集まりに分けて示したもの。
사람의 육체와 정신을 5개의 모임(집합, 뭉침)으로 쪼개어 나타낸 것이다.
- 色(しき、梵: rūpa) - すべての物質。
- 色(색, 범어 rupa=루파) - 모든 물질(유물론적인 물질)
- 受(じゅ、梵: vedanā) - 感受作用。
- 受(수, 범어 vedana=웨다나, 베다나) - 감수작용
- 想(そう、梵: saṃjñā) - 表象作用。
- 想(상, 범어 samjna = 삼즈냐) - 표상작용
- 行(ぎょう、梵: saṃskāra) - 意志作用。
- 行(행, 범어 samskara = 상스카라) - 의지작용
- 識(しき、梵: vijñāna) - 認識作用
- 識(식 , 범어 vijnana = 비즈나나, 위즈냐나) - 인식작용。
十二処[編集]
십이처
十二処(じゅうにしょ)または十二入(「処」は梵: āyatana) - 12の知覚を生じる場。六根、六境[5]。
십이처 또는 십이입( 처는 범어 = 산스크리트어: ayatana 아야타나) - 12개의 지각을 일으키는 곳. 육근, 육경.
後に「処」の字をつけて呼ぶこともある。
나중에는 "처"의 글자를 붙여서 부르는 경우도 있다.
「処」とは、阿毘達磨倶舎論においては、心と心作用(心所)の生じてくる門(生門(しょうもん))のこと[3]。
"처"라는 것은 '아비달마구사론'에 있어서, 심(마음)과 심(마음)의 작용(심소)이 생겨나는 문(생문)이다.
- 六根(ろっこん、梵: ṣaḍ-indriya) - 主観の側の六種の器官[6]、感官[7]のこと。
- 六根(육근, 산스크리트어 샤드-인드리야) - 주관적인 측면에서 본 6가지 종류의 기관, 감각기관이다.
- 六内入処(ろくないにゅうしょ)とも。
- 육내입처등도 같은 말이다
- 眼(げん、梵: cakṣus) - 視覚能力もしくは視覚器官
- 眼(안, 눈 안, 범어 caksus = 칵슈스) - 시각능력 또는 시각기관
- 耳(に、梵: śrotra) - 聴覚能力もしくは聴覚器官
- 耳(이, 귀 이, 범어 srotra = 쉬로트라) 청각능력 또는 청각기관
- 鼻(び、梵: ghrāṇa) - 嗅覚能力もしくは嗅覚器官
- 鼻(비, 코 비, 범어 ghrana = 그라냐) - 취각능력 또는 취각기관
- 舌(ぜつ、梵: jihvā) - 味覚能力もしくは味覚器官
- 舌(설 혀 설, 범어 jihva = 지흐바 지흐와) - 미각능력 또는 미각기관
- 身(しん、梵: kāya) - 触覚能力もしくは触覚器官
- 身(신 몸 신, 범어 kaya 카야) - 촉각능력 또는 촉각기관
- 意(い、梵: manas) - 知覚能力もしくは知覚器官
- 意(의 뜻 의, 범어 manas = 마나스) - 지각능력 또는 지각기능
三科 - Wikipedia
ja.wikipedia.org
안-이-비-설-신(눈-귀-코-혀-몸)이라는 5개를 오근(五根)이라고 부르며,
- 六境(ろっきょう、梵: ṣaḍ-viṣaya) - 客観の側の六種の対象[6]、感官の対象[7]のこと。
- 六境(육경, 범어 sad-visaya = 샤드-위샤야) - 객관적으로 존재하는 측면에서 본 여섯가지 대상, 감관의 대상이다.
- 六外入処(ろくげにゅうしょ)とも。
- 육외입처등과 같다.
六境 - ウィクショナリー日本語版
出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ja.wiktionary.org
- 顕色けんじき[12](いろ)と形色ぎょうしき[12](かたち)の2種類に分たれ、また、青、黄、赤、白、長、短、方、円、高(凸形)、下(凹形)、正(規則的な形)、不正(不規則な形)、雲、煙、塵、霧、影、光、明、闇の20種に分たれる[13]。
- 良い香りと悪い香り、適度な香りとそうでない香りの別により4種に分たれる[13]。
- 甘さ、酸っぱさ、しおからさ、辛さ、苦さ、渋さの6種に分たれる[13]。
六根、六境(、後述の六界)の順序は、現在の法を対象とするものを先にし、四大種によって作られた色(所造色)のみを対象とする眼、耳、鼻、舌を先にし、より遠い対象に作用するものを先にし(眼、耳の順)、より速やかに明らかに作用するものを先とし(鼻、舌の順)、あるいは感覚器官の位置の高いほど先とし(眼、耳、鼻、舌の順で、身は多くの部分がこの下にあるからこれらの次とし、意はとどまる場所がないから最後となる)[17]。
十八界[編集]
十八界(じゅうはちかい、梵: aṣṭādaśa-dhātavaḥ) - 18の知覚認識の要素。六根、六境、六識。
後に「界」の字を付ける[5]。「界」とは、種族、種類のこと[3]。
六根、六境、六識の十八界を数え上げるのは、主観の心が客観の対象をとらえるのはそれぞれの器官を通じてである、という考えに立っている。見る心(眼識)は視覚器官(眼)を通して、色・形(色)をとらえる。聴く心(耳識)は聴覚器官(耳)を通じて音(声)をとらえる、といった具合である[18]。- 眼識 (げんしき、梵: cakṣur-vijñāna) - 視覚する心
- 耳識 (にしき、梵: śrotra-vijñāna) - 聴覚する心
- 鼻識 (びしき、梵: ghrāṇa-vijñāna) - 嗅覚する心
- 舌識 (ぜっしき、梵: jihvā-vijñāna) - 味覚する心
- 身識 (しんしき、梵: kāya-vijñāna) - 触覚する心
- 意識 (いしき、梵: mano-vijñāna) - 識知し思考する心[19] [9]
五識[編集]
眼識、耳識、鼻識、舌識、身識を五識(ごしき)[20]もしくは前五識(ぜんごしき)とよび、それに対して意識を第六識とよぶ[21]。
前五識は現在の対象に向かってしかはたらかず、過去や未来の対象にははたらかない[21]。それに対して意識は過去・現在・未来の対象に向かってはたらく[21]。すなわち過去を追憶し、未来を予想することができる[21]。
前五識の対象は、眼識ならば色、耳識ならば声、に限られるが、意識の対象は(狭義の)法のみならず、すべての法(ダルマ)にわたる[21]。なお、意識は前五識を統括するものではない[21]。
十二処・十八界の表[編集]
十二処・十八界については下表のとおり[1][22][23][24]。
十二処六根六境| 眼(げん)(眼根(げんこん)、眼処(げんしょ)) | 色(しき)(色境(しききょう)、色処(しきしょ)) |
| 耳(に)(耳根(にこん)、耳処(にしょ)) | 声(しょう)(声境(しょうきょう)、声処(しょうしょ)) |
| 鼻(び)(鼻根(びこん)、鼻処(びしょ)) | 香(こう) (香境(こうきょう)、香処(こうしょ)) |
| 舌(ぜつ)(舌根(ぜっこん)、舌処(ぜっしょ)) | 味(み)(味境(みきょう)、味処(みしょ)) |
| 身(しん) (身根(しんこん)、身処(しんしょ)) | 触(そく) (触境(そっきょう)、触処(そくしょ)) |
| 意(い)(意根(いこん)、意処(いしょ)) | 法(ほう)(法境(ほうきょう)、法処(ほっしょ)) |
十八界
| 眼界(げんかい) | 色界(しきかい) | 眼識界(げんしきかい)(眼識(げんしき)) |
| 耳界(にかい) | 声界(しょうかい) | 耳識界(にしきかい)(耳識(にしき)) |
| 鼻界(びかい) | 香界(こうかい) | 鼻識界(びしきかい)(鼻識(びしき)) |
| 舌界(ぜっかい) | 味界(みかい) | 舌識界(ぜっしきかい)(舌識(ぜっしき)) |
| 身界(しんかい) | 触界(そくかい) | 身識界(しんしきかい)(身識(しんしき)) |
| 意界(いかい) | 法界(ほっかい) | 意識界(いしきかい)(意識(いしき)) |
心・意・識の同義[編集]
心と意と識とは、阿含以来、同義語と解されている。それは五蘊であれば識蘊、十二処であれば意処であるが、十八界でいうと七心界(眼識界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界、意識界、意界)となる[25]。意界(意根)は、現在にはたらいた六識が、次の刹那過去に去ったとき、それが引き続いて現在に生起してくる次の識のよりどころとなる[25]。五蘊の識蘊は有情の生のよりどころとなるものを指すため、それと対応する十八界の意界は有漏の識のみを意味し、七心界に属するすべての識(有漏、無漏の識をともに含む)を意味しない[26]
その他[編集]
- さらに経典によっては、下記を加える[27]。
- 六識身(ろくしきしん、過去の記憶) - 眼識身・耳識身・鼻識身・舌識身・身識身・意識身
- 六触身(ろくそくしん、外界との接触) - 眼触身・耳触身・鼻触身・舌触身・身触身・意触身
- 六受身(ろくじゅしん、六觸所生受身/六觸因縁生受[28]、外界との接触により生じる判断) - 眼受身・耳受身・鼻受身・舌受身・身受身・意受身
- 六想身(ろくそうしん、六觸所生想身、外界との接触により生じる知覚) - 色想身・聲想身・香想身・味想身・觸想身・法想身
- 六思身(ろくししん、六觸所生思身、外界との接触により生じる思い) - 色思身・聲思身・香思身・味思身・觸思身・法思身
- 六愛身(ろくあいしん、六觸所生愛身、外界との接触により生じる愛着) - 色愛身・声愛身・香愛身・味愛身・所触愛身・法愛身
- 自らの存在が他のものが同時・同所に生起することを妨げ、同一空間内で他と抵触するもののことを有対といい、十色界(五根および五境)は有対である[29]。
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ^ a b 図解雑学 般若心経 2003, p. 97.
- ^ 阿含経のほか大乗経典でも、鳩摩羅什訳『摩訶般若波羅蜜経 無生品第二十六』(T0223_.08.0270c01)などにみられる。
- ^ a b c d e 櫻部 1981, p. 69.
- ^ 村上 2010, p. 233~234.
- ^ a b 図解雑学 般若心経 2003, p. 96.
- ^ a b c d e f 櫻部・上山 2006, p. 60.
- ^ a b c 村上 2010, p. 233.
- ^ a b c d e f 岩波仏教辞典 1989, p. 851.
- ^ a b c d e f g h 櫻部・上山 2006, p. 仏教基本語彙(1)-(10).
- ^ 櫻部・上山 2006, p. 94.
- ^ 「意根」 - デジタル大辞泉、小学館。
- ^ a b 櫻部 1981, p. 138.
- ^ a b c d 櫻部 1981, p. 64.
- ^ 櫻部 1981, p. 64-65.
- ^ 五欲とは - ブリタニカ国際大百科事典/大辞泉/大辞林/コトバンク
- ^ 櫻部 1981, p. 73.
- ^ 櫻部 1981, p. 70.
- ^ 櫻部・上山 2006, p. 60-61.
- ^ 櫻部・上山 2006, p. 105.
- ^ デジタル大辞泉『五識』 - コトバンク
- ^ a b c d e f 櫻部・上山 2006, p. 108.
- ^ 櫻部 1981, p. 65.
- ^ 岩波仏教辞典 1989, p. 851-852.
- ^ 櫻部・上山 2006, p. 65.
- ^ a b 櫻部 1981, p. 66.
- ^ 櫻部 1981, p. 70~71.
- ^ 例えば『仏説長阿含経 巻第八 第二分衆集経第五』(T0001_.01.0051c19~26)
- ^ 『雑阿含経 巻第八 一九五』(T0099_.02.0050a13~23)等。また大乗経典の『摩訶般若波羅蜜経 巻第二 往生品第四』(T0223_.08.0231b19~20)にも見られる。
- ^ 櫻部 1981, p. 72~73.
参考文献[編集]
- 頼富本宏 ; 今井浄圓 ; 那須真裕美『図解雑学 般若心経』ナツメ社、2003年。ISBN 4-8163-3544-7。
- 櫻部建 ; 上山春平『存在の分析<アビダルマ>―仏教の思想〈2〉』角川書店〈角川ソフィア文庫〉、2006年。ISBN 4-04-198502-1。(初出:『仏教の思想』第2巻 角川書店、1969年)
- 櫻部建『倶舎論』大蔵出版、1981年。ISBN 978-4-8043-5441-5。
- 中村元他『岩波仏教辞典』岩波書店、1989年。ISBN 4-00-080072-8。
- 村上真完「法(dharma)と存在(bhava)と存在しているもの(sat)」『印度學佛教學研究』第60巻第2号、日本印度学仏教学会、2012年、 892-885頁、 doi:10.4259/ibk.60.2_892。
関連項目[編集]
| この項目は、仏教に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 仏教/ウィキプロジェクト 仏教)。 |
'불교학' 카테고리의 다른 글
| 붓다의 철학, 세계관, 인생의 법칙입니다 (0) | 2023.04.24 |
|---|---|
| 프랑스의 티벳불교와 선불교 - 불교적 지혜 (0) | 2022.05.18 |
| 숲속 스님의 인생 - The Life of a Forest Monk (0) | 2021.09.17 |
| 브라질에 38m의 불상(佛像)이 세워지다 (0) | 2021.08.30 |
| 요가를 통해서 심층심리를 발견하다 - 팔식론(八識論, 8가지의 심리) (0) | 2021.08.12 |



